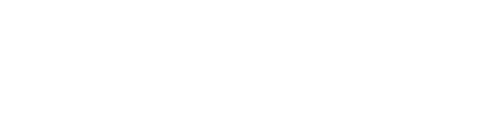SESをビジネスの柱とするIT企業の業態変革
- SESビジネスを柱とするIT企業がどのような考え方でその業態変革を進めるべきか考察する
- 現業への影響が出ない範囲での業態変革を志向する場合、その変革の進め方や考え方のポイントを明らかにする
- プロダクトの開発を志向する場合、営業・マーケティングの仕組みをどのように構築すべきかポイントを明らかにする
SES契約とは
システム開発における顧客と開発会社間の契約形態はかなり大雑把な分け方をすると、完成されたシステムに対して対価が発生する契約と、エンジニアの労働時間に対して対価が発生する契約に大別されます。後者の契約がSES契約(System Engineering Service)と言われており、主に顧客のプロジェクトにおいて常駐で働くエンジニアを提供するモデルとなります。
このSES契約は、派遣法に関連する偽装請負の問題や、働き方改革の文脈における超過労働の温床となっているという議論は数多くありますが、日本に存在する数多のシステム開発はこのSES契約を活用しており、客先常駐型のエンジニアによって大部分が構築されてきた事実は否めません。また、日本のIT業界に深く根付いたこのような仕事の進め方が今すぐ無くなるということは考えにくいものがあります。これらの法的・社会的是非についての議論は別の問題として扱うものとして、ここではあくまでビジネス的な観点からタイトルの通り、SESをビジネスの柱とするIT企業の業態変革について考察します。
業態変革を行う動機
そもそもSESによる顧客サービスの提供を行う企業にとって業態変革を行う動機はどこにあるのでしょうか。経営者にとってみれば、顧客のプロジェクト現場に人を送り込むことでその対価として売上が上がり、未経験者の場合は一定の教育は必要ではありますが、最低限必要なコストは人件費のみなので爆発的な利益を得られることはありませんが、需要(プロジェクト現場)と供給(一定のスキルを保有する社員)がマッチすれば安定的な収益を得られるという点でビジネスモデルとしては成立しています。参入障壁は一般的にあまり高くないと考えられますが、需要サイド、供給サイドの両方が揃っている必要があるので、単純に断罪するには難しいものがあります。
これまで多くのSES契約を主なビジネスとするIT企業の変革をお手伝いするために経営者の方々と話してきた中で、動機は主に以下の3点に集約されます。また、他にも様々な背景が考えられますが、IT業界に関連する世の中の状況の変化は別途記事をまとめる予定です。
- 特に経験者を中心とする採用が非常に難しくなってきている
- 社員数が売上の限界を規定しており、長期的な成長に期待感が薄い
- リーマンショックのような急激な景気の悪化に対する準備をしたい
意思決定フロー
SES契約を主たるビジネスとするIT企業にとって、業態変革を行うことは簡単なことではありません。例えば、現在稼働中のプロジェクトのエンジニアを一定の期間、新たなプロダクトを作るための特任チームに配属する意思決定を行ったとします。その場合、本来稼働していれば得られたはずの売上を失うと共に人件費は今まで通りとなり、機会損失も含めると1名を非稼働状態にしてプロダクト開発などを行うためには相当な覚悟を持って行う必要があるからです。
以下はあくまで議論をスムーズに進めるための簡単な意思決定フローです。今の状況に満足していないという前提があるにしても、その解決の方向性は意思によって大きく変動します。

多くのIT企業の経営者と議論していると、最もありがちなパターンは、2も3もYesと回答し、Aの「社員数が制約とならないビジネスモデルへの大変革」を行いたいという話に一度はなるものの、現実的なリスクが見えてくると、Bの「現業に影響が出ない範囲で徐々にモデルチェンジをしていきたい」という結論になるパターンです。無論これを否定するものではなく、前述のとおり、すでに稼働している社員の機会損失も考慮に入れると会社の存続を賭ける覚悟が必要となりますが、規模が拡大し事業が安定してきたらという考えが元々あったものの、いつまで経っても安定していると思えない状況は想像に難しくありません。
また、よくあるパターンの次点は、すでにプロダクト開発などに乗り出していて、売り先を模索する段階にいる企業です。この場合、2の質問に対してはNoとなり、4の質問もNoで、Dの「新規顧客を獲得するためのチャネル開拓やナーチャリングの仕組みの構築・改善」がテーマとなるパターンです。これは一歩進んでいてこれまでのルート営業を脱却し、新たな営業・マーケティングの仕組みを構築していく段となります。
次章以降で、よるある上記の2パターンについて詳細に見ていくことにします。
段階的な業態変革のアプローチ
現業に影響が出ない範囲で部分的なモデルチェンジを行いながら業態変革を進めるということはどのようなことでしょうか。以下に2つのアプローチを紹介します。

「理想」と「現実」と書いたこの二つのアプローチです。「理想」モデルは、いわゆるウォーターフォール型で描かれた計画に基づき、明確なゴールイメージを持って変革を進めるモデル。「現実」モデルは、様々な取り組みを継続し、失敗を繰り返しながら進めていき、筋の良いアイデアを模索していくモデルです。理想と現実と名付けているのはその名の通り、理想のアプローチができたらとても良いのですが、現実はそうはいかず、むしろ成功している企業には様々な取り組みを継続し、失敗を繰り返しながら新たな事業の芽を見出しています。
なぜ「理想」モデルのアプローチは難しいかというと、軌道修正が無い完璧な計画を立案するためにはそれこそ膨大な投資がかかります。しっかりとしたマーケット調査を行い、入念な設計と共にプロダクトを構築し、さらには販売・マーケティング計画を立て、場合によっては調達も必要になるケースがあります。無論、このアプローチは単に理想論かというとそうではなく、ベンチャー企業ではこのやり方がやりやすいと言えます。なぜなら、集まるメンバーは入社する時点で大きなリスクを会社がとっていることを認識しているわけですし、調達をしている場合は大きな目標に向かって邁進しリスクを取ることが常にVCなどからも要求されることであるからです。
一方の「現実」モデルについてみた場合、このアプローチが簡単であるという認識ではその変革は確実に失敗すると言えます。
失敗を許容し、その中から新たな事業の芽を見出し、継続的に前を見続けて邁進する必要があります。また、近年では各種のスタートアップ企業の実体験を書籍やネットで触れることが容易な環境になってきました。このようなリスクの取り方やアプローチを正と認識する人も多く、これが障害となることも多くあります。
最低限必要な業態変革の軸を設定する
前章の「理想」モデルと「現実」モデルでは、ゴールイメージの持ち方は当然違います。「理想」モデルでは、明確にいわゆるビジョンを立て、その旗の下に仲間を集める必要があります。一方の「現実」モデルですが、ビジョンは必要ないか、という問いに対しては無論Noと言わざるを得ません。
しかしながら、失敗を許容しながら様々な取り組みを今後行っていく上で、それこそスタートアップ企業のようなきらきらしたビジョンを立てられるかというと、単にやることの幅を狭める結果となるようなビジョンであれば、それは作ることで障害となることもあります。ではその軸をどのように設定するべきかというひとつの考え方をご紹介します。

『ナンバーワン企業の法則』のフレームワークを便宜的にお借りします。企業活動は選択と集中であり、図にあるような3軸のいずれかに向いている必要があるという考え方です。右側には、多くのIT企業のプロジェクト現場でよく聞く声です。重要なことはAさん、Bさん、Cさんそれぞれは非常に高いモチベーションを持って仕事に取り組んでおり、会社の発展を強く意識しています。しかし、向いている方向がばらばらなことで、せっかくの高いモチベーションの社員たちは身動きが取れず、せっかくのアイデアも打ち消しあってしまう結果になってしまいます。
最低限必要な業態変革の「軸」は、顧客への提供価値に他なりません。きれいなビジョンを作ることも非常に重要である一方で、現業で我々は何を顧客に提供しているのか、なんで我々は選ばれているのだろうか、というような現状認識がスタートとなります。
業態変革の一例
日本における中小IT企業は数多く存在しますが、最近では単にSES契約を行うのではなく、独自の特徴を出している企業が増えてきました。SESビジネスを主とするIT企業がSaaSのサービスを提供し始めるケースはまだまだ稀ですが、奇抜なアイデアをビジネスモデルに適用するよりも成功モデルが存在する変革は失敗するリスクを減らすには有効です。もちろん新規のプロダクトやサービスを構築する場合にはその内容やマーケットの状況によって、そのリスクは大きく変動することは前提です。

既に機能しているビジネスモデルが存在し、大きなリスクを取れない場合、よほど思い入れのあるビジネスでなくては奇抜なアイデアを追い求めるより、自社の現状を把握し、成功モデルから失敗を繰り返しながら事業の変革を推進する方が一定のコントロールの利く状態で変革の実現を推進することができます。無論成功モデルがあるからと言って簡単に実現できることはありませんので、その変革の最中にTry & Errorを繰り返すことにより会社全体の風土・文化を形成していくことが重要で、そのような環境を作っていくことこそがビジネスの継続性を高める武器となっていくことは言うまでもありません。
新規顧客を獲得するためのチャネル開拓やナーチャリングの仕組みの構築・改善
話を意思決定フローに戻し、すでにプロダクト開発などに乗り出していて、売り先を模索する段階にいる企業についても見ていきたいと思います。多くのSESビジネスを柱とするIT企業にとっては、新規顧客に継続的にアプローチする営業方法より既存の強い関係性のある企業との継続的なビジネスに力を入れている方が単純な数字上の観点では正攻法と言えます。一般的に高い稼働率を維持することがこのビジネスモデルにおいては成功要因であり、この稼働率には1か月の穴が大きなインパクトを与えるため、継続的に顧客先にエンジニアを送り込み続けていることが高い収益性につながると考えるのが一般的であるからです。そのため、多くの企業がプロダクトを作ったとしてもこの営業チャネルの開拓の際に大きな壁にぶつかることになります。

これは簡易的に図示した営業・マーケティングの全体像に、会社の現状を把握するためのキークエスチョンを記載したものです。訪問が可能になったコンタクト先のことをリードと言います。リードとは、「手がかり、糸口、きっかけ」といった意味合いでマーケティングでは多用される言葉です。営業・マーケティングを考えていく上では、このリードを獲得する段から、最終的な提案・契約までの段までの流れを高い精度でコントロールしていくことが重要となります。以下のようなステップで状況を把握します。
- リード獲得は十分かどうか、既存営業だけに頼った営業になっている場合は新規顧客の獲得チャネルを確保する必要がある。さらに例えば新たなリードを獲得するための展示会などを出展することは可能か、準備ができているか
- 新規顧客への対応は十分にできているか、その際に何を提示し、何に価値を感じ取ってもらっているのか
- リードナーチャリング(見込顧客の育成)ができているか。そもそも機能として存在するか、継続的にアプローチすれば顧客となってくれそうなのに放置していないか、放置してしまっていることが把握できる仕組みができているか
- デモ提供やトライアルなどの顧客を説得できる材料は揃っているか、スムーズな契約交渉までの段取りが準備されているか
SESビジネスの営業を行っている場合、平均的に見て総社員数の10%程度の営業体制があるものと想定されます。平均的に獲得している案件規模にも寄りますが、現在既存顧客への営業や稼働中のプロジェクトの状況把握のため走り回っている営業担当に単に現在不足しているパーツを埋めることを指示してそれは無茶ぶりと言わざるを得ません。商材こそITに関係するものであるとしても、売り方は全く異なることを念頭にオペレーションを構築していく必要があります。例えばSaaSのようなサブスクリプションモデルのプロダクトを作り上げたとして、既存の顧客でそれを採用してくれる会社は余程の関係性ができている場合は受け入れられる可能性があっても、多くの場合強いニーズを持っている新たな顧客を探す必要があります。さらに言えばプロダクト販売の場合において見込顧客1社あたりにかけられる時間は決定的に違いますので、外部委託のテレオペ部隊などの調達も視野に入れるべきでしょう。また、新規性が高いプロダクトを扱うのであれば、ナーチャリングという顧客を育てるというプロセスを意識することが非常に重要となってきます。